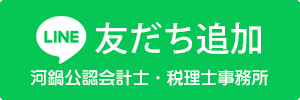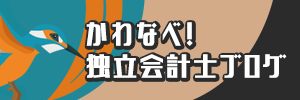今回のコラムは「租税法の不確定概念」についてです。
税法には曖昧な表現がたくさんあります。
たとえば、役員給与の支払が損金不算入となる「不相当に高額な金額」、扶養義務者相互間の生活費、教育費の贈与が非課税となる「通常必要と認められるもの」などです。
具体的な範囲が不明な表現では課税されるか予測がつかず、不安定なものになります。
租税法では、これらの表現を「不確定概念」と呼んでいます。
目次(各項目に飛べます)
課税要件明確主義に反する不確定概念
税金は私たちの大切な財産から納めるものですので、課税は財産権の侵害にあたります。
一方で、憲法では租税は法律に基づいて課されるものとされています(租税法律主義)。
課税要件は法律で定め(課税要件法定主義)、明確に示すこと(課税要件明確主義)で恣意的な課税を防ぎます。
不確定概念とされる「不相当に」「通常必要」といった曖昧な表現は、課税要件明確主義に反します。
役員給与がどれくらいの水準であれば損金になるのか、扶養義務者間の資産移転がどれくらいまでなら非課税となるのか、わからないまま申告書を提出し、そこから税務署の裁量で判断がなされるのでは、納税者は個々の行為に慎重にならざるを得ません。
不確定概念への対処法
租税法の山本守之先生は、不確定概念であっても「経済的取引の実態にあった課税という面では納税者にも意義がある」ことに言及されています。
たとえば、社長に高額な給与を支払っていても会社の業績が良く、大きな利益を計上している場合は妥当なものとして損金となる場合もあるでしょう。
また、扶養義務者間の贈与で受贈者に生活水準を維持させる必要があるものの、本人には費用を負担する資力がなく、贈与者には資力がある場合、その贈与は非課税となる可能性があります。
評価通達6項の適用による課税
ところで、近年、相続税の財産評価において課税の公平を論拠に、評価通達6項を適用して通達評価が「著しく不適当」と認め、税務署の算定する価額で恣意的に課税しようとする事例が頻発しています。
これも不確定概念を利用した課税です。
通達に法的拘束力はないと言えますが、法令を補完する機能を担っており、6項による課税処分は今後も増えるのではないかと懸念されます。
納税者には個々の行為に際して税法の趣旨・目的と経済的取引の実態に則しているかの判断が求められそうです。

弊事務所では1人1人のお客様に真摯に寄り添い、満足度の高い相続税申告やコンサルティングを実施しております。
相続税申告の見積りや初回相談は無料で行っております。
まずは、お問い合わせページからご連絡をお待ちしております。
福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者

公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。