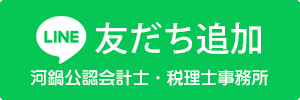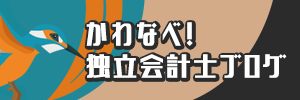今回のコラムは「防災庁が創設された点」についてです。
日本は世界的に見て自然災害の多発地帯です。
震度5を超える地震が毎年発生し、台風による被害も生じています。
2024年元旦では、能登半島における地震が発生し、さらには豪雨による被災が加わり多くの命が亡くなりました。
首都直下地震、南海トラフ巨大地震などの発生も懸念されています。
とりわけ、南海トラフについては、政府の地震調査委員会は今後30年以内に起きる確率について、これまでの「70%から80%」を「80%程度」に引き上げています。
ところで、災害における問題の一つが「災害関連死」です。
日本では、ひとたび災害が起こると、被災者の方々は避難所で厳しい生活を強いられます。
阪神大震災では避難生活の心身の疲労などで体調を悪化させて死亡する人がクローズアップされ、そこから災害関連死という考え方が生まれました。
2016年に起きた熊本地震では、222人が避難生活の疲労やストレスに起因する災害関連死に認定されました。
これは、地震による建物倒壊などの直接死の4倍にあたります。
また、2024年の能登半島地震では、災害関連死は同年末時点で276人と熊本地震を超えています。
被災者が安心して避難生活を過ごせるよう、避難生活環境の整備が求められています。
こうした状況を受け、防災業務の企画立案機能の強化、平時から万全の備えを行うことへの必要性が高まっています。
昨年、石破政権が発足し、政府は2026年度に防災庁を創設すると発表しました。
防災庁では国民を災害から守るため専任の大臣を置き、防災業務の企画立案機能を抜本的に強化し、平時から万全の備えを行うといいます。
また、災害対応についてはエキスパートを十分な人数で備える予定です。
石破総理いわく「本気の事前防災」を実現するための組織が防災庁というわけです。
現時点では、発足に向け、災害に関する知見を集約し災害関連死などの「人災」を防ぐ仕組みを模索しています。
2024年11月、防災庁設置準備室が発足し、看板掛けを行いました。
トイレやキッチンカー、ベッド・風呂等々を配備できるような官民連携体制の構築、また、被災地の情報を迅速かつ効率的に収集する防災DX(デジタル・トランスフォーメーション)などが、防災庁の創設により飛躍的に前進することが期待されています。
具体的に実施すべき事項を挙げると、すべての避難所で「スフィア基準」を満たすことがあります。
スフィア基準というのは、紛争や災害の避難者が尊厳ある生活を送るために、避難所環境の最低基準を具体的に設定したものです。
正式名称は「人道憲章と人道対応に関する最低基準」で、1997年に国際赤十字などが策定しました。
基準には、1人当たり3.5平方メートルの居住スペースや20人につき最低1基のトイレといった具合に、詳細の基準が定められています。
現行の法律でも災害対策基本法があり、災害が起こった時の対処について法整備はあります。
ただ、同法ですと、災害応急対策の主体は市町村となっています。
小さな自治体の場合、役所には数十人から数百人の人材しかいないところもあります。
また、大規模の災害の場合、町長も助役も総務課長も亡くなるケースもあり、自治体が主体となることには無理があります。
防災庁があれば、インフラの復旧など、市町村任せにせずに、国が全国から業者を集め、どんどん進めることが可能になります。
何より、蓄積したノウハウを今後に残し、共有することもスムーズに行えることも防災庁設立の大きなメリットとされています。

弊事務所では1人1人のお客様に真摯に寄り添い、満足度の高い相続税申告やコンサルティングを実施しております。
相続税申告の見積りや初回相談は無料で行っております。
まずは、お問い合わせページからご連絡をお待ちしております。
福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者

公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。