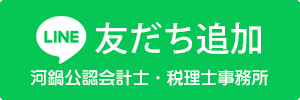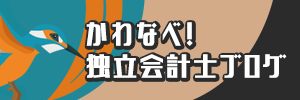子どもたちは大喜びでした(^^)
平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。
雪が降って寒波の厳しさが続く毎日となっております。
体調を崩されないようお気を付けください。
それでは、2025年2月の事務所だよりをお届けします。
目次(各項目に飛べます)
2月の税務
| 2/10 | ● 1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(納期の特例を受けている方は対象外) |
| 2/28 | ● 12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消 費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ● 3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ● 法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ● 6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) ● 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> ● 消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> |
| その他 | ● 前年分贈与税の申告(申告期間:2月3日から3月17日まで) ● 前年分所得税の確定申告(申告期間:2月17日から3月17日まで) ● 固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付(2月中において市町村の条例で定める日) |
【相続】相続放棄の手続きの実際とその流れ
相続における3つの選択
相続が発生すると相続人となる者は、単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する)、もしくは限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ)、または相続放棄(遺産の相続を放棄しプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない)のいずれかを選ぶことになります。
相続放棄を選択するのは、一般的に借金が多い場合と考えられますが、借金がなくとも相続に関わりたくない、財産分与ゼロでハンコを押すのはしゃくだなど、他の理由であっても自分の意思で選べます。
相続放棄の手順
① 家庭裁判所へ相続放棄を申述する
相続放棄の申述は、民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所にしなければならないと定められています。
申述書に申述内容を記入し、被相続人の住民票除票又は戸籍附票や申述人(放棄する人)の戸籍謄本など(=申述人の被相続人との関係性により必要書類は変わってくる)を添付して家庭裁判所に書類を送ります。
② 家庭裁判所から「照会書」が届く
申述後、家庭裁判所から「照会書」が届き、(1)誰かに強要されたり、(2)他人が勝手に手続きしたり、(3)相続放棄の意味がわからず手続きしていないかなど、その申述が本人の真意によるものかの確認がなされます。
書類をよく読んで、真意である旨を「回答書」に自筆で記載し期限内に返送します。
③ 「相続放棄申述受理通知書」で完了
家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」(相続放棄が無事に認められた旨の通知)が届いて手続き完了となります。
なお、他の相続人が相続手続きをする際に「相続放棄申述受理証明書」の原本が必要となります。
通常は、受理通知書が届いた後に受理証明書の交付申請を行いますが、事前に受理証明書の交付申請を行えば、受理通知書に同封されて受理証明書も届きます。
相続放棄のデメリット
相続放棄が完了すると後から撤回できないため、相続放棄完了後に莫大な財産が見つかったとしても、その財産を引き継ぐことはできません。
また、他にも個々の事情で発生するデメリットもあり得ます。
放棄に際しては、司法書士などの専門家に相談しながら手続きすることをお勧めします。

相続放棄をしていても生命保険金(死亡保険金)は受け取ることが出来るけど、非課税枠を受けることができないなど、相続税の計算も少し特殊になるので注意です!
年金と税制について
老齢年金は課税、障害・遺族年金は非課税
公的年金給付は受給権者の生活の安定のため、支給を受けた金額が租税等の課税対象とならぬよう課税対象から外されています。
ただし、例外的に老齢年金は課税対象とされています。
これは、老齢への備えとして保険料納付実績に比例した給付であり、一種の貯蓄的な性格や給与の後払い的な性格があること、保険加入中に被保険者として納付した保険料は社会保険料控除として拠出段階で既に非課税であること等を勘案したものとされています。
障害年金と遺族年金はあらかじめ発生を予期できないリスクに対応して給付を行うもので非課税とされています。
公的年金は公的年金控除の対象
公的年金等の収入は雑所得に区分され、公的年金等控除額を差し引いて、所得金額を計算します。
公的年金控除の額は定額控除40万円と定率控除(50万円を差し引いた後の年金の収入に応じて、25%、15%、5%と段階的に減少)を合計し、合計額と最低保障額(国民年金基金、65歳以上は110万円、65歳未満は60万円)の大きい方の額になります。
公的年金控除は基礎年金、厚生年金、厚生年金基金、国民年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金(企業型・個人型iDeCo)等が対象です。
老齢年金でも一定額以下は非課税
単身者で公的年金控除の最低保障額110万円と基礎控除48万円に支払った医療保険料、介護保険料等の社会保険料控除を加えた額が所得年金収入158万円に社会保険料の額を加えた額以下の場合は、課税所得がないので、所得税は非課税になります。
住民税を見ると公的年金等控除最低保障額110万円を差し引いた額が均等割非課税基準以下の場合は非課税です。
非課税基準は自治体により異なりますが、東京23区や指定都市の基準は同じです。
年金に所得税がかかる場合は、日本年金機構が年金支給額から所得税を源泉徴収して国に納付します。
公的年金等以外の所得が20万円を超える場合や公的年金等の収入が400万円を超える場合は確定申告が必要です。

インフルと最近はコロナもまた再流行しているので、本当に体調管理に気をつけましょう!
2月も引き続き宜しくお願い致します!

弊事務所では1人1人のお客様に真摯に寄り添い、満足度の高い相続税申告やコンサルティングを実施しております。
会計・税務顧問や相続税申告のお見積り、初回のご相談は無料で行っております。
まずは、お問い合わせページからご連絡をお待ちしております。
福岡県那珂川市・春日市の公認会計士・税理士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者

公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。